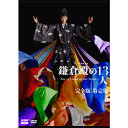鎌倉殿の13人
第25回 2022年6月26日放送
本編タイトル「天が望んだ男」
紀行コーナー:旧相模川橋脚(神奈川県茅ヶ崎市)
はい、今回は源頼朝がこの橋の落成供養に出席した帰りに落馬したとの言い伝えのある橋ですね。橋は現代で言うところの便益って非常に高いはずなんですけれども(渡し舟とか不便極まりないと思うのですが)、この時代では特に大きな川にかかる橋はなかなか定着しないようです。洪水などで流される他にも、戦になるとすぐ落とされてしまいますしね。現代ですらウクライナでロシア軍からの防衛のために橋を落としたなんてニュースになっていました。それでも橋をかけたと言うのは源頼朝が覇権を握ってこれからは平和な世の中になるとの雰囲気もあったのでしょうか。Wikipediaによると、
鎌倉幕府成立後に妻を亡くした稲毛重成は、出家して相模川付近に寺を建て念仏を唱える日々を送っていたが、相模川の渡し船で命を落とす人々の多さを見て、妻への追福のために橋を架けることを決意すると、建久9年(1198年)に頼朝の許可を得て独力で橋を架けたと伝えられている。
いやー素晴らしいですね。この橋は長くは残らなかったようですが(江戸時代は渡し船)、それでも素晴らしいと思います。
では今回も紀行コーナーのアクセスを見ていきましょう。
えーと、今回は関東の人にとっては難易度は高くないと思います。茅ヶ崎駅からバス一本ですからね。ただちょっと「上級者向け」かなあとは少し思います。このサイトで上級者向けと言うのはですね、観光地ではなくて単に遺跡や石碑が住宅地や野原にぽつんとある感じのところを言っているつもりです。ですので石碑などを見るだけでも当時に思いを巡らせることができる人向けという感じでしょうか。関東の人でふらっと散歩がてらに見に行くとかは良いのかなと思います。
茅ヶ崎駅から「旧相模川橋脚」最寄りの「今宿」バス停へは神奈川中央バスの[茅06][茅41][茅48]系統で行けますが、一番本数が多いのは[茅06]で日中1時間2本ですかね。茅ヶ崎駅北口発で行き先は「平塚駅北口」になります。平塚駅の方が便利な人は平塚駅経由でも良いですね。[茅06]は平塚営業所管轄、[茅41][茅48]は茅ヶ崎営業所管轄とかで路線図が別々なのですが、まあ[茅06]の方を見ておきましょう。

茅ヶ崎駅と平塚駅のちょうど真ん中あたりが今宿バス停になります。時刻表はこちら
www.kanachu.co.jp
国指定史跡 旧相模川橋脚
バス停からはこんな感じです。徒歩5分程度ですね。
今宿バス停はこんな感じです。
上記のストリートビューは東向きのアングルになっていて、茅ヶ崎駅から平塚駅行きのバスが停まるバス停が映っています。画面奥が旧相模川橋脚の方向ですね。片側一車線ですが、国道1号線だけあってロードサイド店がひしめいている感じですかね。
で、旧相模川橋脚そのものは以下です。左に立っている2つの四角い縦長の石碑にはそれぞれ「史跡 旧相模川橋脚」と「天然記念物 旧相模川橋脚」と書いてあります。関東大震災の時の液状化現象で浮き出てきたと言うことで天然記念物という扱いにもなっているのですね。今見えている木はレプリカらしいですが。本当に鎌倉時代のものなの?という気もしますが、年輪年代測定という手法で大体の年代は合っていることが確認されているようです。
場所としては上記ストリートビュー画面の反対側には大きなニトリがありまして、いやあロードサイドですなあという感じのロケーションになっています。
御霊神社(ごりょうじんじゃ)(茅ヶ崎市)
一緒に紹介されていた2つの場所も近くにあります。御霊神社ですが、まず「御霊神社」という名の神社は日本各地にあるので注意ください。紹介されたのは茅ヶ崎市の御霊神社になります。御霊神社というのは怨霊を鎮めるために建立されたところが多いようです。今回紹介された場所で言うと、頼朝が義経の怨霊を見て落馬したと言われることから源義経を祭ったと言うことですね。
旧相模川橋脚からの徒歩ルートを貼っておきます。途中で次に紹介する弁慶塚を経由しています。バス停で言うと上で紹介した同じ路線の今宿バス停から2つ茅ヶ崎駅よりの「茶屋町」バス停が一番近いと思います。
ストリートビューはこちら。。。
衛星写真だと以下のような感じです。左下への道が入り口の方向ですね。
弁慶塚(平塚市)
もう一つコーナー内で紹介されていたのが弁慶塚です。弁慶塚も各地にありますが、こちらは鶴嶺八幡宮の一の鳥居の近くにあります。源頼朝が落馬したのがこの鶴嶺八幡宮付近であったと言うことのようです。場所的には鶴嶺八幡宮の一の鳥居は国道1号線沿いにありまして、バス停で言うと今宿バス停から1つ茅ヶ崎駅よりの「町屋」バス停のそばになります。御霊神社の最寄りの「茶屋町」と旧相模川橋脚の最寄りの「今宿」の間ということですね。
「町屋」バス停のストリートビューが以下です。道の両側にバス停があるのがわかるでしょうか?そして奥に見えている赤い鳥居が「鶴嶺八幡宮の一の鳥居」になります。
そして弁慶塚の所在地なんですが、今は私有地にあるようなんですね。
弁慶塚
源義経に仕えた僧兵の武蔵坊弁慶を祭った塚で、鶴嶺八幡宮参道脇にある。義経一族の霊を慰めるために造ったと伝わる。現存する塚は元の場所から1982年(昭和57年)に場所を少し移して作り直された。現在は私邸である。
衛星写真だと以下のような感じです。左下に見えている(スマホだと見切れている?)鳥居が鶴嶺八幡宮の一の鳥居、その前の通りが国道1号線ですね。完全に私有地ですが、入ること自体は問題ないようですので、迷惑にならない範囲で訪問しましょう。
ちなみに、鳥居をくぐってすぐの参道の左側に「弁慶塚」という石碑がありますが、こちらは弁慶塚そのものではないので気を付けてくださいね。以下のストリートビューは参道に入ってから振り返って鳥居の方向を見ているアングルです。松の木の後ろに石碑があるのが分かるでしょうか?
ところでこの鶴嶺八幡宮ですが、個人的に参道が非常に雰囲気が良いように感じました。散策するならこういうところが良いなと思える場所ですね。一の鳥居のある弁慶塚から鶴嶺八幡宮までの徒歩ルートが以下です。
上記のGoogle Mapsのルートだと上の方の鶴嶺八幡宮に近いところがまっすぐになっていないように見えますが、車が入れないだけでまっすぐに鶴嶺八幡宮まで歩くことができます。
さらにちなみに、Wikipediaによると、
建久9年(1198年)12月5日、頼朝がこの橋の竣工式に出席した帰りに、平家の亡霊に驚いた馬が暴れて川へ落ち、寒さに触れて病を得て翌年1月に死亡したという説がある。この時、警護の武士10人が責任をとって自害し、その墓が龍前院の境内の10基の五輪塔であるとも言われている。
うわっ怖って思うのですが、この10基の五輪塔は造られた時期が少しずつ違っているらしく、そういう言い伝えがあるにはあるよというところですね。龍前院というのは鶴嶺八幡宮の裏手にありまして、この10基の五輪塔を衛星写真で見ると以下のようになっています。
モデルルート
さて東京駅からのモデルルートですけれども、茅ヶ崎駅ですからね。必要ですかね?でもまあ一応書いておきます。
めちゃめちゃ余裕のある時間で組んでみました。東京駅からだと予定立てる必要ないんじゃないかって気がします。ちなみに青春18きっぷでは元が取れません。。。あ、そう言えばいつも東京駅起点のルートで不公平じゃないかって思う方もいらっしゃるかもしれませんね。そうですね、不公平だと思います。というか偏向してますよね。なんですが、筆者が東京近郊在住のためこれからも東京駅起点でルートを組ませていただきたいと思っております。あしからず。。。
※休日ダイヤでルートを組んでいます。
※実際に訪問する場合にはくれぐれも最新の情報をご確認ください。
それでは今回はこの辺りで。
過去の調査リストはこちらから
taiga-kikou.hatenablog.com